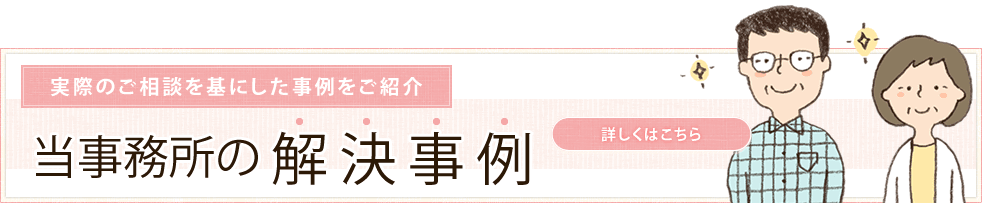藤沢駅徒歩5分
ひなた司法書士事務所
ご相談・お問い合わせ
営業時間 平日9時から17時
土曜日9時から11時(予約面談のみ)
定休日 日曜日・祝日
司法書士が外出、ご相談対応中のことがありますので、
事前のご予約をお願いします。
営業時間外の予約についてもお気軽にご相談ください。
想いをかたちにする遺言書の
作成は当事務所にお任せください。
今のうちに遺言書を作成してみませんか?遺言書を作成しておけば将来の相続手続きがスムースに進められたり、相続の際のもめ事を防げる場合もあります。
当事務所ではお客様のお話を詳しく伺い、お客様のお気持ちを反映し、将来の相続手続きが円滑に進められるよう最適な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
- 藤沢駅北口から徒歩5分
- ご相談は無料です。
- お見積もりは無料です。
- 土曜日も予約可能です。


遺言書作成サポート
当事務所の公正証書遺言の作成サポートのご費用
| ご 費 用 下記の1~3の合計額になります。 |
1.司法書士報酬遺言者1名につき11万円(税込) この報酬に含まれる内容遺言書の文案作成公証人との打ち合わせ 証人2名の立会い その他必要な事項、アドバイス 税理士等のご紹介※必要に応じて 2.公証役場の手数料3.その他の実費公的証明書取得手数料郵送費 交通費 定額小為替手数料 など 以下のような事案は加算がございます。 詳しくは無料で見積もりをしますのでお気軽にご相談ください。
|
公正証書遺言作成のご費用
公証人手数料は必ず必要となり、司法書士にその文案作成等の依頼をした場合はその報酬が必要になります。
公証人手数料は、大まかに下記のようになります。
| 目的財産の価額 | 手数料 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 1万1000円 |
| 1000万円まで | 1万7000円 |
| 3000万円まで | 2万3000円 |
| 5000万円まで | 2万9000円 |
| 1億円まで | 4万3000円 |
※1 これに全体の財産が1億円未満の場合は遺言加算として1万1000円加算されます。
※2 遺言書全体の手数料を算出する場合、相続または受遺する人全員の手数料を合算します。
※3 公証役場で作成した場合です。出張した場合は費用が加算されます。
※4 遺言書は、原本・正本・謄本の3部作成されますが、それに必要な紙の枚数1枚につき250円かかります。
※5 祭祀の主宰者を指定する場合は、1万1000円加算されます。
※6 公証人手数料の正確な計算方法は、お近くの公証役場へご確認されるか、下記の日本公証人連合会ホームページをご参照ください。
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
例1)3000万円の財産を1人に相続させる場合
手数料(2万3000円)+遺言加算(1万1000円)+用紙代(約3000円)=約3万7000円
例2)相続人が2人で、1人に5000万円、1人に3000万円の財産を相続させる場合
手数料(2万9000円+2万3000円)+遺言加算(1万1000円)+用紙代(約3000円)=約6万6000円
- 遺言書の作成を検討されている方へ
- 遺言書の作成をご検討いただきたい11の場面
- 司法書士を利用するメリット
- 公正証書遺言の作成の際に
お客様にしていただくこと、司法書士が行うこと - 当事務所に遺言書作成サポートをご依頼いただき
公正証書遺言を作成するときの流れ - そもそも遺言とは(遺言の種類・公正証書遺言とは)
- 遺言の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
- 公正証書遺言とは
- 相続・推定相続人・相続割合とは
- 遺言書を作成したいときは
- 遺言をするメリット
- 遺言のタイミング
- 公証役場まで行くことが出来ない場合は
- 遺言執行者とは
- 遺留分とは
- 生前贈与、遺言の作成のどちらがよいか
- 遺言書作成の際の税務について
遺言書の作成を検討されている方へ
こんなお悩みはありませんか?
- だれに相談したらよいのかわからない。
- どのような段取りで進めたらよいかわからない。
- 費用がどのくらいかかるかわからない。
- 急いで書かなくてもいいのでは?

* お気軽にご相談ください *
遺言書の作成に年齢は関係ありません。万が一のために今、遺言書を作成して将来に備えませんか?状況が変われば遺言は何度でも書き直すことができますので、現時点で考えられる最善の遺言書を書いておきましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。ご面談時にお客様のお話をしっかりと伺います。
手続きの進め方をわかりやすくご説明させていただきます。合わせて必要となる書類のご案内、お見積もりをさせていただきます。
公正証書遺言の場合、公証役場との打ち合わせ段取りはすべて当事務所で行いますので、公証役場に行くのは一度だけで大丈夫です。
遺言書の作成をご検討いただきたい11の場面
- ケース1.夫婦間に子供がいない場合
- ケース2.再婚し、前の配偶者との子とは疎遠になっていて、現在の配偶者との間の子に財産を残したい場合
- ケース3.連れ子がいる場合
- ケース4.推定相続人に疎遠な親族がいる場合
- ケース5.内縁の妻・夫に財産を残したい場合
- ケース6.身より(推定相続人)がいない場合
- ケース7.障がいのある子の将来が心配な場合
- ケース8.自分の死後の財産の引継ぎで相続人に面倒をかけたくない場合
- ケース9.自分の相続人となる者の間で話し合いがまとまらないと予想される場合
- ケース10.あらかじめ誰にどの財産を相続させるか決定している場合
- ケース11.相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合
公正証書遺言の作成時に司法書士を利用するメリット
弊事務所をご利用いただいた場合、以下のようなご支援をさせていただきます。
最適な遺言書文案の作成
遺言書の作成にあたっては、家族・親族関係、財産状況、どのように財産を遺したいかなど、様々なご事情を伺いながら、最適な遺言書となるべく文案の作成をいたします。
遺言書の作成によってトラブルが起こることをご懸念される場合、なるべくトラブルを回避できるような文案をご提案させていただきます。
また、相続税の問題がある場合は、税理士とも協力してご支援いたします。
公証役場との事前打ち合わせをすべて代行します。
公証役場への文案提出、必要書類、公証人手数料の確認など、遺言書を作成する当日までの段取りは全て司法書士が代行しますので、平日公証役場になかなか行くことが出来ない方でもスムースに段取りを進めさせていただく事が可能です。
ご依頼者様が公証役場に行くのは、遺言書作成の当日のみで大丈夫です。
司法書士と事務員が証人となります。
司法書士と事務員の2名が証人を務めさせていただきますので、ご依頼者様に証人を探していただく必要はございません。
司法書士、事務員には守秘義務がありますので安心してご依頼いただけます。
公正証書遺言の作成の際に
お客様にしていただくこと
- 電話かメールで日時を予約
- 来所時に参考書類、認印、身分証明書(運転免許証など)を持参
- 必要書類の取得(司法書士がご案内します。)
- 公証役場に司法書士と一緒に訪問
司法書士が行うこと
- ご依頼者様に手続きの流れやご費用についてご説明
- 遺言書の原案を作成
- 公証役場と事前の打ち合わせ
- 公証役場へお客様と同行
- 司法書士と司法書士事務所事務員で証人を務めます。
当事務所に遺言書作成サポートをごいらいいただき
公正証書遺言を作成するときの流れ
弊事務所をご利用いただいた場合、以下のようなご支援をさせていただきます。
01
まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
簡単なご質問にお答えしたり、どのように手続きを進めさせていただくかなどをご説明させていただいたり、ご相談の日時などを決めたりします。
02
お話をしっかりとお伺いします。
どのようなお気持ちで遺言書を作成しようとお考えになったかや、どのような遺言を作成されたいか等をしっかりと伺います。
お話を伺ったうえで、どのような遺言書にすべきかや文案の方向性をご提示したり、ご用意いただきたい書類をご案内させていただいたりします。
ご依頼た場合のご費用についてもご説明させていただきます。
03
司法書士が文案を作成します。
文案が完成しましたら、ご依頼者様にご確認をしていただきます。修正があれば修正をし、ご依頼者様に文案に最終確認をいただきましたら、司法書士が公証役場に連絡し、日程の調整をし、公証人手数料の確認をさせていただき、司法書士からご依頼者様にご連絡します。
04
公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。
遺言書作成日に、公証役場に行くか、遺言者のご自宅、入院先等に公証人に来てもらいます。
そこで、司法書士および事務員の2名が証人として立ち合い、公証人が遺言書の内容を読み上げますので、遺言者にはその内容に間違いがないか確認していただきます。
内容に問題がなければ、遺言者、証人2名、公証人が遺言書の原本に署名押印します。
この署名をもって公正証書遺言が完成します。
その場で公正証書遺言の正本と謄本の2通が手渡されます。(署名した原本は公証役場で保管されます。)
最後にこの場で、公証人手数料、司法書士報酬のご精算をさせていただきます。

遺言に関するQ&AQ&A
そもそも遺言とは?
「遺言」とは、死後のために残す最終の意思表示です。
自分の財産を誰にどのように相続させるのかを決めたり(相続分の指定)、相続人以外の第三者に財産を贈りたい場合(遺贈)、相続人を廃除したい場合(一定の理由により相続権を奪うこと)、認知していなかった子を認知したい場合など、民法という法律で定められている事柄を遺言に記すことにより、法律上の効果を発生します。
民法で決められたこと以外にも、法律上の効果はありませんが、自分の希望や思いなども記すことができます。
必要な事柄だけでなく、思いや希望を一緒に書いておけば、残された者にも遺言の趣旨が伝わりやすくなるでしょう
遺言の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
遺言書には様々な形式がありますが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的といえるでしょう。
公正証書遺言の場合、公証人に内容を伝え、証人2名の立会いのもと作成します。
公正証書遺言作成にあたっては公証役場の費用がかかり、証人を2名用意する必要があります(知り合いなどがいない場合は公証役場が手配してくれます。)が、下記「公正証書遺言とは」に記載されているように、様々なメリットがあります。
自筆証書遺言の場合、手軽に作成できる点、費用がかからない点などのメリットがありますが、形式に不備があれば無効になったり、その恐れがある点、遺言で出来ることと出来ないことの整理がされておらず結果的に遺言の実現が困難・不可になる恐れがある点、また、発見されなかったり隠匿されたりする恐れがあり保管が難しい点などのデメリットもあります。
どの形式で遺言書を作成するかは、長所・短所をしっかりと考えて決めましょう。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言する内容を説明し、その説明に基づき公証人が作成します。
大まかな流れのイメージとしては、事前に公証人と遺言の内容の打合せをし、遺言書作成日を決めます。遺言書作成日に証人2名、遺言者、公証人が集い、遺言の内容を確認し、署名押印などがされることにより遺言書が完成します。
公正証書遺言の主な特徴・メリットとして次のようなことが挙げられます。
1.>内容、形式とも安心・確実なものが作成できること。
2.紛失や偽造の恐れがないこと。
3.自筆証書遺言では必要になる家庭裁判所の検認手続が不要であること。
4.遺言者が120歳になるまで、遺言書を公証役場で保管しておいてくれること。
遺産に関する争いが起こりそうな場合や、残される方の不安を取り除くには、やはり公正証書にしておくのが一番でしょう。
公正証書遺言の場合は作成に費用がかかりますが、今まで一生懸命築いてきた財産を残された方に安心して引き継ぐために、出来得る対策をしておけば、より安心・満足して暮らすことができるのではないでしょうか。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
| メリット | メリット |
| ■形式の不備がない。 ■公証役場で保管してくれる。 ■裁判所での検認手続が不要である。 |
■費用がかからない。 ■手軽に作成できる。 |
| デメリット | デメリット |
| ■費用がかかる。 ■証人が2人必要になる。 |
■記載内容を間違えば無効になることがある。 ■発見されない恐れがある。 ■隠蔽される恐れがある。 ■裁判所での検認手続が必要になる。 |
相続・推定相続人・相続割合とは?
1.相続とは?
相続とは、ある人の死亡(法律用語では亡くなった方のことを「被相続人」と言います。)により、その人の財産に関する地位を、配偶者や子供など一定の身分関係のある人(「相続人」と言います。)が引き継ぐことです。
2.法定相続人とは?
法定相続人とは被相続人が亡くなったときにその財産を承継する権利のある人のことを指します。この権利関係は民法で定められています。
配偶者がいる場合は常に相続人となり、被相続人の子などの直系卑属が第1順位、被相続人の直系尊属は第2順位、被相続人の兄弟姉妹は第3順位となります。なお、相続する権利を有する人が被相続人よりも先に死亡している場合には、一定の身分関係を有する人に代襲相続権があります。
ただし、相続する権利のある人でも、欠格事由に該当したり、排除されたり、被相続人遺言の内容次第では相続する権利がない場合もあります。
3.推定相続人とは?
「推定相続人」とは、将来相続が開始した場合において相続するべき人のことをいいます。
4.相続割合とは?
民法に定める「法定相続」による相続割合は以下のようになります。ただし、相続人全員で遺産分割協議をする場合、各相続人の相続割合は話し合いなどで自由に決めることができます。また、実際の相続にあたっては、寄与分や特別受益を考慮する必要がある場合もあります。
相続人が配偶者と子の場合 ー 配偶者1/2 子1/2
※ 子が複数いる場合は、子の数で等分します。
相続人が配偶者と直系尊属の場合 ー 配偶者2/3 直系尊属1/3
※ 親が複数いる場合(父と母など)、人数で等分します。
父母がおらず祖父母がいる場合、祖父母が相続人となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 ー 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※ 兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の数で等分します。
ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
配偶者がいない場合 ー 子が全部相続
配偶者、子がいない場合 ー 直系尊属が全部相続
配偶者、子、直系尊属がいない場合 ー 兄弟姉妹が全部相続
遺言書を作成したいときは
一般的な公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリットをよく考えたうえ、遺言書の種類を決めてください。
遺言には財産や身分に関係する大切なことを書きますので、十分に考えをまとめてから作成しましょう。
まずは、自分の財産の内容にはどんなものがあるのか、誰が相続人なのか、どのくらいの割合で相続する権利があるのか、相続が発生したときに問題がおこりそうかどうか等、紙に書いて遺言の作成に必要な情報をまとめてみましょう。
遺言では、自由に財産の分配方法などを決められますが、一部の相続人をあまりにも優遇したり、今まで話していたことと全く違う内容であったりすると、せっかくの遺言も残された人々の新たな紛争のもとになりかねません。
それぞれの相続人の立場をよく考え、気を配った内容にしておくことも大切です。
遺言に書く内容を専門家に相談してまとめてほしいとき、遺言の内容で将来相続人の間でトラブルが発生する恐れのあるときや、複雑な遺言を残す場合など、司法書士などの専門家に相談してみてください。
遺言をするメリット
遺言をするメリットのひとつは、相続発生後の相続人の間の争いを予防できることです。「うちに限って揉めることはない。自分の考えは口頭で伝えれば十分だ。」と考えていても、実際に相続が発生した後は、お金のことも含まれますので残された人々の関係がどのように変わるかは分かりません。
遺言がなく遺産分割協議をした場合、遺産の額にかかわらず、それぞれの相続人はなるべく多く財産を取得したいのが本当のところでしょうから、遺産分割協議をきっかけに関係が崩れることもあり得ます。
今できる間に様々な事情を考慮し、誰にどのように財産を残すのか遺言にまとめておけば、相続人間の争いを予防し、負担を減らすことができるでしょう。遺言では、財産を誰にどのように相続させたいか、遺贈したいかを自分の思うように決めることができます。
例えば、同居の家族やお世話になった人に財産を多く残したければ、そのような遺言をしておくこともできます。
但し、自分の配偶者、子、親が相続人になる場合に、その人たちには財産を相続させたくないので全く財産を残さずに、別の人に財産を残すとする遺言も有効ですが、配偶者、子、親には遺留分があるので、その範囲で財産を請求することができます。
また、遺言の内容をしっかりと実行してもらうには、公正証書による遺言を作成して、その中で遺言執行者を指定するのが最も確実な方法でしょう。
遺言のタイミング
一般的には、「遺言書を作成するのは高齢になってから。」というイメージが強いかも知れません。
しかし、遺言をするには一定の判断能力が必要です。
判断能力が低下してから作成すると無効になることもあり得ますし、病気などで作成すること自体が困難になることもあります。
遺言書は15 歳以上であれば作成することができますし、また、いつでも書き直すことができます。
元気なうちからいざという時に備えて、自分の意思を残すため、家族のため、トラブル防止のために、「マイホームを手に入れたとき」、「定年退職したとき」、「子供が成人したとき」など、自分のタイミングを見つけて作成しておくのが良いでしょう。
公証役場まで行くことが出来ない場合・自署が出来ない場合は?
公証役場まで行くことが出来ない場合
病気や高齢などの事情により、公証役場まで行くことが出来ない場合でも、公証人の手数料加算、日当、交通費等が必要になりますが、自宅、病院、老人ホームなど遺言者が居るところまで公証人と証人が赴き、その場所で遺言を作成することが出来ます。
なお、遺言書を作成する当日までに進めるべき事柄(文案の作成、必要書類や費用の確認、遺言書作成日の日程の調整など)についても、弊事務所に遺言書作成サポートのご依頼をいただいた場合には、最初に司法書士が遺言者の自宅等に訪問し、遺言者との打ち合わせのうえ、上記事柄をすべてサポートさせていただきますので、よりスムースに遺言書作成をしていただくことが可能です。
自署が出来ない場合
高齢や身体的な障がい等が原因で、遺言書に、遺言者が自分で署名できない場合、公正証書の場合は、公証人が法律によって与えられた権限により、公証人が遺言者の署名を代筆することが出来ます。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、相続人の代理人として相続財産を管理し、遺言の内容や趣旨に沿って遺言の執行に必要な行為を行う者のことをいいます。
遺言執行者は遺言で指定されている場合が多いですが、指定されていない場合や指定された遺言執行者が先に亡くなっている場合、必要であれば家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求できます。
遺言執行者には未成年者及び破産者はなれませんが、相続人や遺贈を受けた者でも遺言執行者になることが出来ます。
ただ、遺言の内容によっては相続人や受贈者の利害関係が複雑に絡む場合がありますので、トラブルが予想されるときは、公平な第三者や弁護士や司法書士等の専門家に、遺言執行者への就任を依頼したほうが無難でしょう。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)の生活保障などの観点から、遺言によっても排除できない一定の相続分です。
たとえ遺言書で「第三者に全財産を遺贈する。」としても、被相続人の配偶者、子、親などには、遺留分があるので「遺留分減殺請求」ができます。
後で争いが起きないよう、遺留分には十分配慮して遺言書を残すことをお勧めします。
なお、遺留分は減殺請求をして初めてその権利を取り戻すことができます。
この請求は相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈又は贈与があったことを知ってから1年以内にしなければなりません。
また相続開始から10年経過すると、相続開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても請求できなくなります。
生前贈与、遺言の作成のどちらがよい?
結論から申し上げますと、ケースバイケースです。
例えば、複数いる子のうち、自宅を同居している子の名義に変えたいときに、今のうちに変えておく場合は生前贈与、死亡した時に変えたい場合は遺言書を検討することになります。
この場合、生前贈与を選択した場合、自分の生きている間に引継ぎが出来るので安心できる一方、自分の所有物ではなくなるので、今後老人ホームに入ることを希望する際に入居金に充てることが出来なくなることも考えられますし、子が勝手に売却してしまうこともないとはいえません。
一方、遺言書の作成を選択した場合、名義が変わるのは自分の死後ですが、今後、状況が変わった場合でもいまだ名義は自分のままなので、売却したり遺言書の内容を変更したりすることも可能です。
上記はあくまでも一例ですが、実際にはご自身の今後の将来設計や、贈与税、相続税の検討もしたうえで判断していくこととなります。
弊事務所にご相談いただく場合には、ご事情を伺い、必要に応じて税理士と協力して最適なご選択をしていただけるよう、提案させていただきます。
遺言作成の際に検討すべき税金についてADVICE
天野税理士のワンポイントアドバイス!
税金のご相談はお任せください!
遺言書を作成する際には、将来の相続税のことも検討しておく必要があります。
遺産相続の際は相続税、そのほか不動産取得税や相続後売却するときには譲渡所得税なども発生する場合がございます。
遺言書を作成する際には、税金面の検討、特に節税対策も行っておくと安心して手続きを進めることができます。
当事務所では各種ご相談、税務申告手続きの代行も行っておりますので、トータルでサポートいたします。